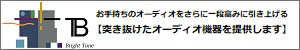アナログマスターを192kHz/24bitデジタルリマスタリング
クリプトン、HQM STOREでチューリップのベスト盤をハイレゾ配信
新田氏は当時のアナログ/デジタル変換がどのように行われていたのか、赤裸々なまでに語ってくれた。「CDの急速な普及の背景には、アナログ音源のデジタル化が不可欠でした。しかし、このアナログ/デジタル変換時のマスタリングの方法に問題があったのです。こうした作業を担当したのは、主に経験の足らない若いエンジニアたちでした。彼らは変換に用いる機器のパラメーターを「ゼロ」(初期状態)にして、後は機械に触るなと厳命されていたのです。そうすることが、マスターに忠実な音質を維持してデジタル化できると本気で考えられていたのですね」(新田氏)。
「もちろん、メーター上のゼロがゼロではないことは常識です。アンプやコンソールにはそれぞれの機器特有の音、特性があって、マスターに忠実な音にするためには、詳細な設定が必要だったはずなのに」と新田氏。マスターと音が変わってしまったという叱責を海外のコンテンツホルダーからうけることを恐れたサラリーマン根性がその根底にあったと、当時を分析する。
新田氏はマスターテープという概念についても、こう語る。「わたしたちが60年代後半から70年代に行ってきた録音において、トラックダウンの終わった2chを最終マスターだと思ったことは一度もありません。私たちは川口や御殿場の工場に出向き、ノイマンのカッティングマシーンの顕微鏡をのぞきながら針飛びしないように溝を切りました。太い音には太い溝を掘って最後の仕上げをしたのです。だからマスターとは「Scotch 201」アナログテープではなく、耳で確認するしかないラッカー盤だったのです」(新田氏)。
こうした職人芸とも言えるレコードのカッティングへ至るにあたって、新田氏はこんなエピソードも語ってくれた。「ザ・ビートルズの『ヘイ・ジュード』のシングル盤が出たとき、7分を超える長い曲がなんでシングルに収まるのだろうと、カッティングマシーンの顕微鏡で盤面を見てみました。すると、出だしのピアノだけのパートや楽器の数が少ないところはとても細い溝で切ってあり、サビに入ってドラムが入ると、針飛びしないように太く溝を切ってある。手動のマニュアル操作で、こうした調整を行っていたのです」(新田氏)。
今回のチューリップのハイレゾ音源は、そんな新田氏の言うマスターに限りなく近づいたという印象を受けたという。「192kHz/24bitでチューリップの曲を聴いたとき、当時のスタジオの感覚や空気感まで思い出して、久々に興奮してしまいました。技術によってどんどん劣化していった音が、やっともとのあるべきかたちにもどってきたという印象さえ受けました」と新田氏は結んだ。
「もちろん、メーター上のゼロがゼロではないことは常識です。アンプやコンソールにはそれぞれの機器特有の音、特性があって、マスターに忠実な音にするためには、詳細な設定が必要だったはずなのに」と新田氏。マスターと音が変わってしまったという叱責を海外のコンテンツホルダーからうけることを恐れたサラリーマン根性がその根底にあったと、当時を分析する。
新田氏はマスターテープという概念についても、こう語る。「わたしたちが60年代後半から70年代に行ってきた録音において、トラックダウンの終わった2chを最終マスターだと思ったことは一度もありません。私たちは川口や御殿場の工場に出向き、ノイマンのカッティングマシーンの顕微鏡をのぞきながら針飛びしないように溝を切りました。太い音には太い溝を掘って最後の仕上げをしたのです。だからマスターとは「Scotch 201」アナログテープではなく、耳で確認するしかないラッカー盤だったのです」(新田氏)。
こうした職人芸とも言えるレコードのカッティングへ至るにあたって、新田氏はこんなエピソードも語ってくれた。「ザ・ビートルズの『ヘイ・ジュード』のシングル盤が出たとき、7分を超える長い曲がなんでシングルに収まるのだろうと、カッティングマシーンの顕微鏡で盤面を見てみました。すると、出だしのピアノだけのパートや楽器の数が少ないところはとても細い溝で切ってあり、サビに入ってドラムが入ると、針飛びしないように太く溝を切ってある。手動のマニュアル操作で、こうした調整を行っていたのです」(新田氏)。
今回のチューリップのハイレゾ音源は、そんな新田氏の言うマスターに限りなく近づいたという印象を受けたという。「192kHz/24bitでチューリップの曲を聴いたとき、当時のスタジオの感覚や空気感まで思い出して、久々に興奮してしまいました。技術によってどんどん劣化していった音が、やっともとのあるべきかたちにもどってきたという印象さえ受けました」と新田氏は結んだ。